 Conte sua história › Yashiju sha › Minha história
Conte sua história › Yashiju sha › Minha história
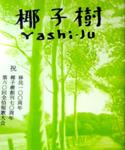
Yashiju sha
São Paulo / SP - Brasil87 anos, Poetas de tanka
- Perfil completo
- Enviar mensagem
- Enviar link por e-mail
- Nenhum comentário
平川 忠志 - 移民船の思い出

私にとって「移民船の思い出」とは一体どんな思い出だろう。なにしろサントスに上陸した年月日さえはっきりしていない。急いでイデンチダーデを探す。そこに記入されているのは一九三五年六月二十八日になっている。これが初めてブラジルの地を踏んだ日であった。当時私は八歳、尋常小学校の二年生であった。私たち一家は両親と祖母と六人の兄弟と一人の従兄弟の構成家族であった。
私たちが故郷を出たときのことはわりとよくおぼえている。小学校の同級生全員で「ゆけゆけ同胞海越えて、遠く南米ブラジルに」の歌を唄って見送ってくれた。そして神戸へ向う汽車の窓から富士山が見えた。私たちの故郷は山梨県の富士山の麓であった。やがて神戸の移民収容所についた。あの小説「蒼氓」にも出てくるこの収容所、思いうかぶのは、高い丘の上の収容所の大きな食堂で多数の人たちとにぎやかに食事をした。まるで修学旅行にでも行っているような楽しい食事だった。そして神戸港から、移民船モンテビデオ丸でドラを鳴らしながら出航していったのだろう。
最初に寄航したのはホンコンであった。港の電灯が一面に海に映って美しい夜景であった。その後は記憶はぼやけ、シンガポール、ケープタウンとか、ダーバンとか、インド洋を進んでいったのだろう。来る日も来る日も、海、海、海であった。アフリカの港だったのだろうか。そこの人たちは黒人で頭に白い布をまいていた。とに角暑かった。やたらに暑かった。黒い大波が押し寄せて来た日もあった。
この航海中に赤道祭というのが行われ、姉たち少女らはみんなで踊った。なん人かの青年たちがブラジルの国歌、つまりイノ・ナショナールを唄ってくれた。いやに長ったらしい歌だった。でもこの赤道祭は楽しかった。そのうちに移民の中の一人の子供が亡くなり、みんなで水葬を行った。なんとなく子供心にも悲しかった。海の中に沈んでゆく子供、悲しいようなさびしいような気持だった。私たち移民の子供は同船の子供たちと遊び又よくケンカした。時には両方の親たちもそれぞれの郷里の方言でやり合っていた。鹿児島県の人たちだったのだろう、その言葉はまるっきり分らなかった。
やがて四十幾日間の船旅を経てサントス港に着いた。それから、当時のひどいブラジルの汽車で奥地へ向った。あのチエテ河をバルコで渡り、緑の地獄といわれていた風土病と毒蛇と猛獣の住みかであったチエテ移住地、私たちはそこで一年少々綿つくりをしたのち、サンパウロ近郊に移転したのであった。よく母たちが泣きながら「こんなところへ来て」とこぼしていたのを思い出す。
移民生活もすでに五十年以上すぎてしまった。両親も三人の兄弟もすでに亡い。が、私たち一家の子孫、曾孫まで生れ、移民の後裔はこのブラジルの大地にしっかり根をおろしている。
Enviada em: 14/05/2008 | Última modificação: 14/05/2008
Todo mundo tem uma história para contar. Cadastre-se e conte a sua. Crie a árvore genealógica da sua família.
Árvore genealógica
Nenhuma árvore.Histórias
O que é Yashiju
鳥越 歌子 - 移民船の思い出
川上 美枝 - 移民船の思い出
井本司都子 - 移民船の思い出
藤田朝日子 - 移民船の思い出
田中 朝子 - 移民船の思い出
酒井 祥造 - 移民船の思い出
平川 忠志 - 移民船の思い出
金城ヤス子 - 移民船の思い出
Vídeos
- Nenhum vídeo.
» Galeria de fotos
- Nenhuma foto.
Áudios
- Nenhum áudio.
As opiniões emitidas nesta página são de responsabilidade do participante e não refletem necessariamente a opinião da Editora Abril

Este projeto tem a parceria da Associação para a Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil



